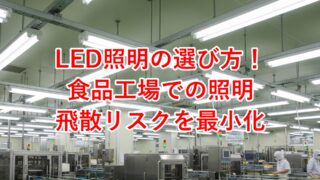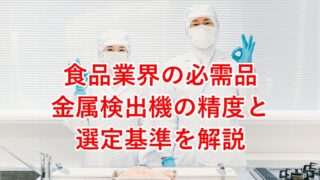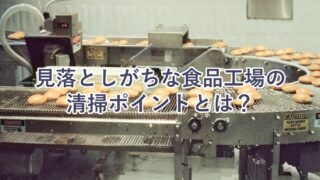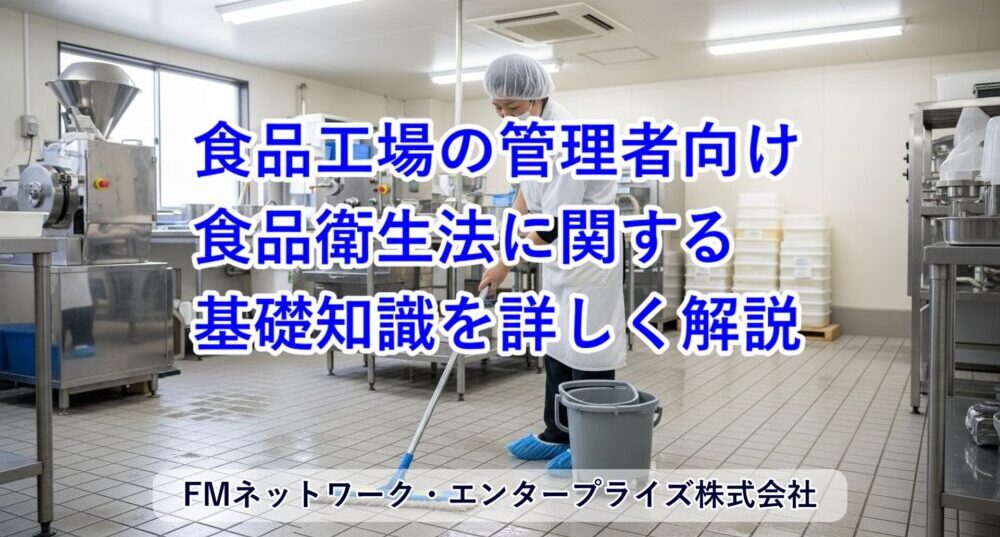食品を製造・加工・販売するすべての事業者にとって、食品衛生法は事業の根幹をなす重要な法律です。特に食品工場の管理者にとって、この法律を理解し遵守することは、単に法的義務を果たすだけでなく、消費者の健康を守り、企業の信頼を維持し、ひいては事業の継続性を確保するために不可欠です。
近年、食品偽装や異物混入、食中毒といった問題が後を絶たず、食品に対する消費者の目は一層厳しくなっています。ひとたび食品事故が発生すれば、企業イメージの失墜、損害賠償、行政処分、そして最悪の場合、事業停止に追い込まれる可能性もあります。
本記事では、食品工場の管理者の方々が、食品衛生法に関する基礎知識を体系的に理解できるよう、その目的、主な改正点、具体的な規制内容、そしてHACCP制度化の意義について詳しく解説します。食品安全マネジメントの基礎を固め、日々の業務に活かしていただくための一助となれば幸いです。
1. 食品衛生法の目的と基本原則

食品衛生法は、食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。その基本原則は以下の3点に集約されます。
- 食品の安全性の確保:
有害な物質の混入や微生物汚染などにより、食品が人の健康を損なうことのないよう、衛生的な取り扱いを義務付けています。 - 国民の健康の保護:
安全な食品を提供することで、食中毒や食品による健康被害を未然に防止し、国民の健康を保護します。 - 適正な表示の推進:
食品に関する正確な情報を提供することで、消費者が適切な選択を行えるようにし、不当な表示による被害を防止します
これらの原則に基づき、食品の生産から最終的な消費に至るまでの全段階において、衛生管理や表示に関する様々な規制が設けられています。
2. 食品衛生法の主な改正と背景
食品衛生法は、社会情勢の変化や科学技術の進展、国際的な食品安全基準の動向に合わせて、度々改正されてきました。特に近年では、以下の改正が食品工場に大きな影響を与えています。
2-1. 2003年改正:リスク分析の導入とトレーサビリティの強化
2003年の改正では、食品安全行政に「リスク分析」の考え方が導入されました。これは、科学的な知見に基づき、食品が健康に与えるリスクを評価し、適切な管理措置を講じるというものです。また、食品の安全性を確保するためには、問題発生時に原因究明や回収を迅速に行う必要があることから、食品の「トレーサビリティ(追跡可能性)」の確保が重要視されるようになりました。
2-2. 2018年改正:HACCPの制度化と広範な規制強化
2018年の改正は、食品衛生法における最も大きな転換点の一つです。この改正により、原則としてすべての食品等事業者に対し、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害分析重要管理点)に沿った衛生管理の実施が義務化されました。この背景には、国際的な食品安全基準との整合性を図り、日本の食品の国際競争力を高めるという狙いがあります。
また、HACCPの制度化以外にも、以下の点が強化されました。
- 広域的な食中毒事案への対応強化:
都道府県をまたぐ広域的な食中毒発生時に、国が主体的に関与し、情報共有や対策を強化できるようになりました。 - 食品用器具・容器包装の規制強化:
ポジティブリスト制度の導入などにより、食品と接触する器具や容器包装の安全性確保が強化されました。 - 健康食品に関する情報収集・分析体制の強化:
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品など、健康食品に対する関心の高まりを受け、健康被害情報の収集・分析が強化されました。 - 営業許可制度の見直し:
HACCP制度化に伴い、営業許可業種の見直しや、新たな届出制度が導入されました。
3. 食品衛生法の具体的な規制内容

食品衛生法は、多岐にわたる規制を定めていますが、食品工場の管理者として特に理解しておくべき主要な規制内容を以下に解説します。
3-1. 営業許可と届出制度
食品事業を行うためには、原則として都道府県知事(保健所設置市・特別区にあっては市長・区長)の営業許可が必要です。2018年改正により、許可業種が見直され、HACCPに沿った衛生管理の実施義務の対象となるすべての食品等事業者は、原則として何らかの届出を行うことが義務付けられました。
- 営業許可: 食中毒のリスクが高い特定の業種(例:飲食店、食肉販売業、乳製品製造業など)に対しては、引き続き営業許可が必要です。許可取得には、施設の構造や設備、衛生管理体制などが基準を満たしていることが求められます。
- 営業届出: 許可業種以外の食品等事業者(例:食品の保存、運搬、販売を行う者など)も、新たに営業届出が必要となりました。これにより、すべての食品事業者の実態を把握し、行政による監視・指導を適切に行うことが可能となります
3-2. 施設・設備の基準
食品工場は、食品の安全性を確保するために、適切な施設・設備を備える必要があります。具体的な基準は業種や規模によって異なりますが、一般的には以下の点が求められます。
- 衛生的な構造:
虫やネズミの侵入を防ぐ構造、清掃しやすい構造、適切な換気設備など。 - 適切な設備:
手洗い設備、消毒設備、冷蔵・冷凍設備、加熱設備、汚物処理設備など。 - 清潔な環境の維持:
定期的な清掃・消毒の実施、HACCPに基づく衛生管理の実施。 - 適切な原材料の保管:
温度管理、湿度管理、交差汚染防止策など。
3-3. 食品添加物
食品添加物は、食品の製造・加工において、保存性の向上、風味の改善、着色などの目的で使用されますが、その使用は食品衛生法によって厳しく規制されています。
- 指定添加物:
厚生労働大臣が安全性を確認し、使用基準を定めたもののみ使用が認められます。 - 既存添加物:
広く使用されてきたもので、安全性に関する評価が引き続き行われているもの。 - 天然香:
植物や動物から得られる天然の香料。 - 一般飲食物添加物:
通常の食品として用いられるもので、添加物として使用されるもの。
食品添加物の使用にあたっては、使用目的、使用量、表示方法などが厳しく定められており、これらを遵守しなければなりません。
3-4. 農薬等の残留基準
農産物や畜産物には、生産過程で使用された農薬や動物用医薬品が残留する可能性があります。食品衛生法では、これらの物質が人の健康に影響を及ぼさないよう、食品中の残留基準が定められています。食品工場では、原材料の仕入れ時に、残留基準を超過したものが含まれていないかを確認する責任があります。
3-5. 危害分析・重要管理点(HACCP)制度
2018年改正で義務化されたHACCP制度は、食品の安全性を確保するための最も重要な管理システムです。HACCPは、以下の7原則12手順に基づいて運用されます。
HACCPの7原則
- 危害要因分析(Hazard Analysis:HA):
原材料の受入から製品の出荷までの全工程において、健康に危害を及ぼす可能性のある生物学的、化学的、物理的危害要因を特定し、その重要性を評価します。 - 重要管理点(Critical Control Point:CCP)の決定:
危害要因を除去または許容可能な水準まで低減するために、管理を確実に実施しなければならない工程を特定します。 - 管理基準(Critical Limit:CL)の設定:
各CCPにおいて、危害要因を管理するための許容範囲(温度、時間、pHなど)を設定します。 - モニタリング方法の設定:
管理基準が守られていることを継続的に監視するための方法(誰が、何を、いつ、どのように監視するか)を定めます。 - 改善措置の設定:
モニタリングの結果、管理基準から逸脱した場合に講じるべき改善措置(原因究明、製品の隔離、再発防止策など)を定めます。 - 検証方法の設定:
HACCPプランが適切に機能していることを確認するための検証方法(記録の確認、抜き取り検査、微生物検査など)を定めます。 - 記録と文書化:
HACCPシステムに関するすべての情報(危害分析の結果、CCP、CL、モニタリング記録、改善措置の記録など)を文書化し、保管します。
HACCPの導入は、食品工場における自主的な衛生管理を強化し、潜在的なリスクを事前に特定して管理することで、食品事故を未然に防ぐことを目的としています。すべての食品等事業者は、事業規模や業種に応じたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画を策定し、実施する必要があります。
3-6. 食品表示
食品表示は、消費者が食品を選択する上で不可欠な情報であり、食品衛生法、JAS法、健康増進法などを統合した食品表示法によって詳細に定められています。食品工場では、製造する食品が以下の表示義務を適切に満たしているかを確認する責任があります。
- 名称:
食品の内容を示す一般的な名称。 - 原材料名:
使用した原材料を、使用した重量の割合の高いものから順に記載。アレルギー物質(特定原材料8品目:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)の表示は特に重要です。 - 添加物:
使用した添加物を記載。 - 内容量:
固形物と液体の合計量、または固形物の量などを記載。 - 消費期限または賞味期限:
未開封の状態で、品質が保持される期限。安全に食べられる期限が「消費期限」、おいしく食べられる期限が「賞味期限」です。 - 保存方法:
消費期限・賞味期限と合わせて、適切な保存方法を記載。 - 製造者等の氏名または名称および住所:
責任の所在を明確にする。 - 製造所または加工所の所在地:
製造が行われた場所を特定する。 - 栄養成分表示:
- 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が義務付けられています。
不適切な表示は、消費者の誤解を招くだけでなく、行政処分の対象となる可能性もあります。表示内容の正確性と分かりやすさを常に心がける必要があります。
3-7. リコール(自主回収)制度
食品事故が発生し、健康被害のおそれがある食品が流通してしまった場合、事業者は速やかにその食品を市場から回収(リコール)する義務があります。食品衛生法では、リコールの際の行政への報告義務や、回収情報の公表などが定められています。食品工場では、万が一の事態に備え、迅速かつ適切にリコールを実施するための体制を事前に構築しておく必要があります。
4. 食品等事業者が講ずべき措置の基準(一般衛生管理)
HACCP制度の導入と並行して、すべての食品等事業者に義務付けられているのが「食品等事業者が講ずべき措置に関する基準」(通称:一般衛生管理)です。これは、HACCP導入の土台となる基本的な衛生管理のことであり、HACCPの前提条件プログラム(PRPs)とも言われます。
一般衛生管理は、以下の項目で構成されます。
- 施設設備の管理:
施設の清掃・消毒、保守点検、排水管理、防虫防鼠対策など。 - 器具等の管理:
器具の洗浄・消毒、保管、保守点検など。 - 使用水等の管理:
水道水の管理、井戸水等の検査、貯水槽の清掃など。 - 廃棄物の管理:
適切な分別、保管、処理など。 - 従事者の衛生管理:
健康管理、手洗い、服装、衛生教育など。 - ねずみ及び昆虫対策:
定期的な駆除、侵入防止対策など。 - 食品等の取扱いの管理:
原材料の受入・保管、製造工程管理、製品の保管・出荷、交差汚染防止策など。 - 設備の管理:
冷却・加熱設備の点検、温度計の校正など。 - 回収・廃棄:
不適合品の管理、自主回収時の対応など。 - 記録の作成と保存:
各管理項目の記録、HACCP記録の保存など。
これらの一般衛生管理が適切に実施されていなければ、HACCPシステムも効果的に機能しません。日々の業務において、これらの項目を確実に実行することが、食品の安全性を確保するための第一歩となります。
5. 食品安全マネジメントシステム(FSMS)と食品衛生法

食品衛生法は、食品安全を確保するための法的最低基準を定めていますが、より高度な食品安全管理を目指す企業は、ISO 22000などの食品安全マネジメントシステム(FSMS)の導入を検討します。
FSMSは、HACCPの原則を組み込みつつ、組織のマネジメントシステム全体に食品安全の概念を統合するものです。これにより、単に法規制を遵守するだけでなく、継続的な改善活動を通じて食品安全レベルを向上させることができます。
食品衛生法におけるHACCPの制度化は、日本の食品事業者にFSMSの基本的な考え方を導入することを促すものであり、将来的にはより多くの企業が国際的なFSMS認証取得を目指す流れが加速すると考えられます。
6. 食品工場の管理者として心がけるべきこと
食品工場の管理者として、食品衛生法を遵守し、食品の安全性を確保するために、以下の点を常に心がけてください。
- 最新情報の把握:
食品衛生法は改正される可能性があります。常に最新の情報を入手し、自社の体制を適合させることが重要です。厚生労働省や地方自治体のウェブサイト、業界団体からの情報などを定期的に確認しましょう。 - 従業員への徹底した教育:
どんなに優れたシステムを導入しても、それを運用する従業員の理解と実行が伴わなければ意味がありません。定期的な衛生教育、HACCPに関する研修などを実施し、すべての従業員が食品安全意識を高く持ち、適切な作業を行えるように指導してください。 - 記録と文書化の徹底:
HACCPプラン、一般衛生管理の実施記録、教育記録など、すべての記録を正確に作成し、適切に保管することが求められます。これは、問題発生時の原因究明や改善措置の検証、そして行政による監査の際に不可欠な証拠となります。 - 継続的な改善:
食品安全に「これで完璧」という状態はありません。HACCPシステムの検証結果や内部監査の結果に基づき、常に改善点を見つけ出し、システムの有効性を高めていく努力が不可欠です。 - 行政との連携:
地域の保健所など、行政機関との良好な関係を築き、必要な情報提供や相談を積極的に行うことも重要です。行政からの指導や助言を真摯に受け止め、改善に繋げましょう。
7. よくある質問(FAQ)と対応策
Q1:
HACCPは難しそうで、うちのような小規模な工場でも対応できるのでしょうか?
A1:
大規模工場向けの「HACCPに基づく衛生管理」と、小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があります。小規模事業者向けのHACCPは、業界団体が作成した手引書を活用するなど、比較的簡易な方法で導入が可能です。まずは自社の規模や業種に合った手引書を探し、参考にすることをおすすめします。保健所や食品衛生協会などでも相談に応じています。
Q2:
従業員が衛生管理の重要性をなかなか理解してくれません。どうすれば良いでしょうか?
A2:
一方的な指示だけでなく、なぜその衛生管理が必要なのかを具体的に説明し、従業員自身に考えさせる機会を設けることが有効です。例えば、過去の食中毒事例を共有したり、異物混入が起きた場合の企業への影響を具体的に示したりするのも良いでしょう。また、定期的なOJT(On-the-Job Training)や、衛生管理に関するクイズ形式の研修なども効果的です。日々の業務の中で、管理者が率先して衛生管理を徹底する姿勢を見せることも重要です。
Q3:
突然、保健所の立入検査が入った場合、どのように対応すれば良いですか?
A3:
まずは冷静に対応し、検査官の指示に従ってください。求められた書類(HACCPプラン、記録類、施設の図面など)を速やかに提示し、質問には誠実に回答します。もし指摘事項があった場合は、その場で内容を十分に確認し、改善計画を明確に伝えます。検査結果は必ず記録し、指摘された事項については速やかに改善策を講じ、必要であれば改善報告書を提出します。
Q4:
食品表示のルールが複雑で、常に最新の情報を追いかけるのが大変です。何か良い方法はありますか?
A4:
消費者庁の食品表示に関するウェブサイトや、地方自治体の食品表示担当部署の情報を定期的に確認することが基本です。また、業界団体が発行している食品表示の手引書や、食品表示に関するセミナーへの参加も有効です。迷った場合は、地域の消費者庁または保健所の担当部署に相談することをおすすめします。専門家(行政書士やコンサルタント)に依頼することも一つの方法です。
8. まとめ:食品安全は信頼の基盤

食品衛生法は、食品の安全性を確保し、国民の健康を守るための羅針盤です。特にHACCPの制度化は、日本の食品安全レベルを国際的な水準に引き上げる大きな一歩となりました。
食品工場の管理者の方々には、これらの法的義務を単なる「やらされ仕事」と捉えるのではなく、自社の食品安全マネジメントを強化し、消費者の信頼を獲得するための重要な機会と捉えていただきたいと思います。
安全で高品質な食品を提供することは、企業の社会的責任であり、持続可能な事業活動の基盤です。本記事で解説した基礎知識を基に、日々の業務における食品安全意識を一層高め、実践に繋げていただければ幸いです。
食の安全を守るために、すべての食品工場が連携し、より安全で豊かな食生活の実現に貢献していきましょう。