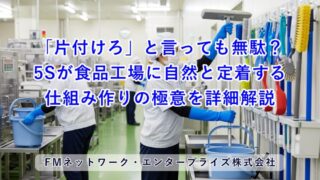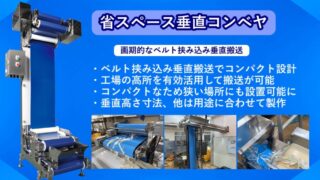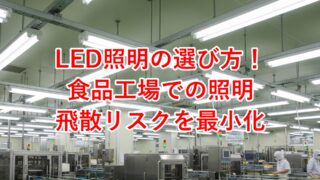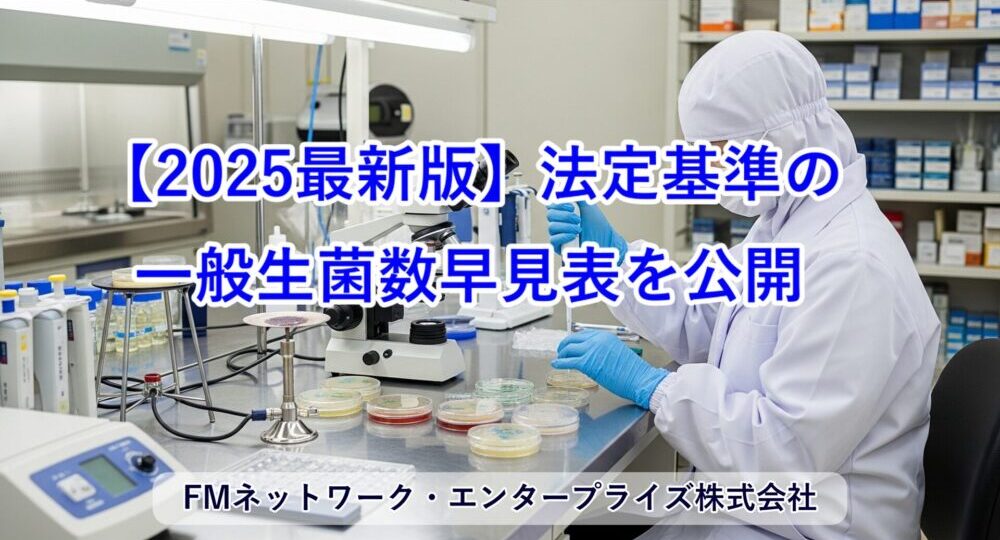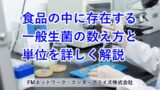食品工場の品質管理担当者や飲食店で仕込みを行う責任者など、「一般生菌数の法定基準って結局いくつなの?」と検索してたどり着いたあなたへ。
本記事では最新規格をもとに、食品カテゴリー別の基準値や測定方法、基準を超えた場合のリスクと対策までを総まとめします。
営業許可更新やHACCP運用に欠かせない実務情報を、図表と具体例でわかりやすく解説します。読み終えたときには、一般生菌数の数字が持つ意味と、自社製品を安全域に保つための行動計画が描けるはずです。
1. 一般生菌数とは?食品衛生法・厚生労働省が定める法定基準の全体像

一般生菌数とは、標準寒天培地を用い35±1℃で48±3時間好気培養した際に発育する中温性好気性および通性嫌気性菌のコロニー総数を指します。
食品中の雑菌汚染度を示す代表的指標であり、食品衛生法では製品ごとに許容上限が細かく規定されています。
2025年改訂ではリスク評価に基づき一部カテゴリーでより厳格な数値へ変更され、HACCP義務化後の運用監視指標として位置づけがさらに強化されました。
消費者が口にする最終製品の安全確保だけでなく、製造工程の管理状態を映す“衛生の鏡”としても機能するため、現場担当者は数値の意味を正しく把握する必要があります。
1-1. 一般生菌数の定義と微生物衛生指標としての位置づけ
一般生菌数は大腸菌群や病原菌の有無とは異なり、「一定条件で育つことができる菌の総量」という広い概念を扱います。
そのため指標菌と比較し直接的な病原性を示すわけではありませんが、生菌数が高いほど食品が不衛生な環境に晒された、あるいは保存管理が不適切であった可能性を推測できます。
HACCPのPRP(前提条件プログラム)においては、一般生菌数が工程管理や設備清掃の有効性を評価する根拠データとして利用され、継続的改善のKPIに採用されるケースも増えています。
1-2. 食品衛生法と厚生労働省通知における規格・基準の変遷(2025年改訂)
食品衛生法では1995年に初めて一般生菌数の具体値が明記され、その後2007年、2013年、2020年の段階改訂を経て、2025年通知で現行の数値体系へと再整理されました。
今回の改訂では特に生食用鮮魚と惣菜カテゴリーで300万cfu/gから100万cfu/gへ、乳児用調製粉乳で500cfu/gから100cfu/gへと大幅な引き下げが行われています。
国際基準であるCodexやEU規則との整合性を確保しつつ、国内における食中毒統計の知見を反映した結果、数値だけでなく測定手法にも表面寒天法からメンブレンフィルター法への代替が追記されました。
1-3. 食中毒を防ぐための目安値:10の5乗・10の6乗を超えると危険な理由
多くの疫学調査では、一般生菌数が10^5〜10^6 cfu/gを超える食品で、サルモネラ属菌や腸炎ビブリオの同時検出率が急上昇する傾向が確認されています。
これは好気性雑菌の増殖曲線上で同じ温度帯を好む病原菌も指数関数的に増えるためであり、食品が人の手や環境から再汚染された際の“ブースター”として作用する点が危険視されます。
結果として加熱後製品でも保存温度逸脱が起きると短時間で危険域へ到達するため、業界では一般生菌数10万cfu/gを“品質警告ライン”、100万cfu/gを“食中毒リスクライン”として運用しているのが実態です。
1-4. 大腸菌群など他の細菌指標との違い
大腸菌群は糞便由来汚染を示唆する狭義の指標であり、非常に低い検出限界値(陰性または10以下/g)で設定されています。一方、一般生菌数は食品が持つ常在菌・環境菌を包含するため、高い数値でも必ずしも病原性があるわけではありません。
しかし大腸菌群が陰性でも生菌数が高い場合、洗浄不足や二次汚染が疑われるので、総合的な衛生評価には両指標を併用することが重要です。
1-5. 一般成分規格との違いと製品表示での扱い
一般成分規格(たんぱく質・脂質・水分など)は栄養価と品質ラベルの正確性を保証するための化学的基準です。これに対し一般生菌数は微生物学的基準であり、製品表示では直接数値を記載する義務はありません。
ただし栄養機能食品や特別用途食品など安全性が厳格に求められるカテゴリーでは、製造所固有記号やロット管理番号と紐づけて社内基準値を公開する企業も増えてきました。
2. 【2026最新版】食品カテゴリー別 一般生菌数法定基準早見表

以下の早見表は厚生労働省「食品、添加物等の規格基準」(2025年4月施行)をもとに、主な市販食品カテゴリーを抜粋したものです。cfu/g(またはcfu/mL)はコロニー形成単位を示し、検体希釈とプレート計数法で算出した値で表示されています。
自社製品に該当する行を確認し、HACCPのCCP設定や出荷判定基準の見直しに活用してください。
| 食品カテゴリー | 法定基準値(cfu/gまたはmL) | 改訂ポイント |
|---|---|---|
| 生食用牛肉・馬肉 | 3.0×10^5 以下 | 従来比−50% |
| 食肉製品(加熱後) | 300 以下 | 据置き |
| 鮮魚介類 | 1.0×10^6 以下 | 新設カテゴリー |
| 寿司・刺身用ネタ | 300 以下 | 強化 |
| 乳酸菌飲料 | 5.0×10^5 以下 | 据置き |
| 粉ミルク(乳児用) | 100 以下 | 厳格化 |
| 冷凍食品 | 1.0×10^5 以下 | 据置き |
| 惣菜・弁当(加熱後) | 1.0×10^5 以下 | 新設 |
2-1. 生肉・食肉製品の基準(300以下は絶対条件?)
食肉製品のうち加熱済みハム・ソーセージは300cfu/gという極めて低い基準が設定されています。
これはリステリア・サルモネラなど熱耐性病原菌の再汚染防止を考慮し、加熱工程が完了した後に包装・冷却・輸送の各ステップで追加的な汚染を極力許容しないという考え方に基づきます。
一般生菌数300以下は製造ラインの空中浮遊菌や人手動線を適切に管理しなければ実現できないため、ISO14644クラス8相当の清浄度を目標にしたエリア分けと定期的な表面拭き取り検査が欠かせません。
2-2. 鮮魚・介類・寿司ネタの目安
生食用の鮮魚介類では1,000,000cfu/g以下が法定基準ですが、刺身や寿司ネタとして提供する場合はより厳しい自主基準として300cfu/gが推奨されています。冷鎖管理がわずかに途切れるだけで腸炎ビブリオが爆発的に増殖するため、仕入れ段階で海水温や漁場情報を確認し、出荷元の一般生菌数証明書を取得することが重要です。
店舗では原魚から柵取り後4時間以内の提供、または0〜2℃のチルド保管を徹底し、衛生規範「刺身・寿司衛生管理マニュアル2024」に準拠した紫外線殺菌機の導入で追加リスクを抑えます。
2-3. 乳酸菌飲料・乳製品の規格値と品質劣化の指標
乳酸菌飲料は製品特性上、善玉菌を大量に含むため一般生菌数そのものが高値となりますが、規格では5.0×10^5cfu/mL以下に抑えるよう定められています。乳酸菌由来の発酵が進みすぎるとpHが過度に低下し、分離や酸敗臭が発生するため、一般生菌数を併用しpH4.0〜4.5が適正域か確認する方法が主流です。
ヨーグルトやチーズでも同様に350万cfu/gを超えると味覚劣化が加速することから、官能検査と合わせてロット判定を行うことで歩留まりを向上させる企業が増えています。
2-4. 冷凍食品・冷凍保存品の許容菌数と成分変化
冷凍食品の基準値1.0×10^5cfu/gは、−18℃以下で保存すれば微生物の増殖が停止するという前提のもと設定されています。しかし解凍・再凍結が繰り返される家庭使用環境では、細胞壁が破壊された菌が下処理後短時間で増殖する恐れがあります。
そのため近年は解凍後の菌増殖シミュレーションを行い、推奨賞味期間を短縮する動きも見られます。
2-5. 惣菜・弁当など一般加工食品の基準値
惣菜・弁当は調理後の冷却から販売まで4時間以内に提供することが多く、法定基準では1.0×10^5cfu/g以下と定められています。ただし加熱後冷却工程がCCPに位置づけられる場合、事業者が設定する管理基準値は10^4cfu/g以下とするのが一般的です。
ホットチェーン維持かコールドチェーン維持かで菌増殖パターンが異なるため、二次元バーコードで最終加熱完了時刻を記録し、陳列棚の温度ロガーと連携した管理が普及しつつあります。
3. 300以下はなぜ『安全ライン』なのか?科学的根拠を徹底解説

一般生菌数300cfu/gという閾値は、WHOが示す食中毒発症確率と菌量の相関研究を基礎に日本独自の疫学データを重ねて設定されています。
300cfu/g以下では病原菌が検出される確率が統計的に5%未満に抑えられ、加えて味や色、香りなど感覚的劣化もほぼ生じないため、品質保証と安全保証を同時に満たす“実務的限界値”として採用されています。
この数値は培地上で1枚のプレートに形成されるコロニーが数えやすい範囲(30〜300)と一致している点も運用上の利点です。
3-1. 腸管出血性大腸菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌との相関
腸管出血性大腸菌O157の感染量は100cfu程度と極めて少なく、一般生菌数が低くても危険な場合があります。しかしO157が存在するケースでは環境汚染が進んでいるため背景菌として一般生菌数も上昇している場合が多く、300cfu/gを超えた時点で追加の病原菌スクリーニングを実施することで早期発見につながります。
黄色ブドウ球菌は10^5cfu/gでエンテロトキシンを産生し始めるため、管理値300はその1/300未満という安全マージンを確保する意味合いもあります。
3-2. 菌数増殖曲線と温度・時間管理のポイント
一般生菌の増殖速度は温度10〜50℃で大きく変動し、特に30〜40℃の“危険温度帯”では世代時間が約20分まで短縮します。理論モデルでは初期菌数30cfu/gが4時間後に960cfu/g、8時間後に3万cfu/gへ達する計算となり、冷却遅延がどれほど危険かを示します。
したがってCCP設定では“中心温度10℃以下を2時間以内に達成”など時間条件とセットで運用し、データロガー付き温度センサーで実測値を記録することが推奨されます。
3-3. 国際規格と比較した場合の安全マージン
Codexではハム・ソーセージ類で500cfu/g以下、EU規則では600cfu/g以下が多い中、日本の300cfu/gは最も厳格な部類に入ります。この差は湿潤な気候と長い物流距離を考慮し、最終消費時までの安全率を2倍以上確保する必要があるためと解釈されています。
輸出を計画する場合は海外規格を上回る国内基準値をクリアしていれば、相手国申請がスムーズに進むメリットもあります。
3-4. 基準超過で発生するリスク事例と対策
2023年には一般生菌数120万cfu/gの弁当が販売され、24名の下痢症状が報告されました。原因は調理後の粗熱取りに3時間要したことと判明し、保健所の指導で急速冷却装置を導入することで再発防止が図られました。
このように基準超過は即リコールや営業停止に直結するため、定期モニタリング、従業員教育、設備投資の三本柱で予防策を講じる必要があります。
4. 一般生菌数の検査・測定方法ガイド

検査方法は大きく分けて平板培養法、選択培地法、迅速キット法の三系統があります。法定検査では標準寒天培地を用いた平板培養法が基本ですが、工程内モニタリングでは時間短縮を目的にATPふき取り検査やリアルタイムPCR法を併用するケースも一般化しています。
以下に代表的な手順と計算ステップを紹介します。
4-1. 平板培地・寒天培地を用いた好気性生菌数試験
1gの検体を無菌操作で99mLのりん酸緩衝生理食塩水に投入し、10^-2〜10^-4まで段階希釈します。各希釈液1mLを滅菌ペトリ皿に分注後、45℃の標準寒天培地を加え混釈し35℃で48時間培養。形成された30〜300コロニーのプレートを選び、CFU=コロニー数×希釈倍数で計算します。
4-2. デソキシコーレイト培地など選択培地での細菌検出方法
食品に特有の背景菌が多い場合、デソキシコーレイト寒天やVRBG寒天で大腸菌群を選択的にカウントし、一般生菌数との比率を求めることで汚染由来の推定が可能です。
選択培地は胆汁酸塩やクリスタルバイオレットによりグラム陽性菌の発育を抑制し、対象菌のみを可視化できる利点がありますが、栄養要求の高い微生物は検出漏れとなる点に注意が必要です。
4-3. 10倍希釈・ml換算による菌数計算ステップ
- 希釈系列作成:10^-1〜10^-6まで連続希釈
- 植え付け:各希釈液1mLを寒天培地へ注ぎ混釈
- 培養後計数:30〜300コロニーのプレートを選択
- CFU算出:コロニー数×希釈倍数=CFU/g
- 平均値:複数プレートの算術平均を求め報告書へ記載
4-4. 外部検査機関への依頼フローと結果の読み方
自社で検査設備が無い場合、公的検査所またはISO/IEC17025認定ラボへサンプルを発送します。検体は冷蔵状態で24時間以内が原則で、依頼書には食品名、製造日、保存条件、検査目的を明記します。
報告書では“一般生菌数 2.1×10^2cfu/g(基準適合)”のように表示されるため、基準値と比較し合否を判断し、CCP逸脱があれば是正処置記録に添付します。
5. 製造・加工現場の衛生管理:一般生菌数を抑える環境・殺菌対策

現場での一般生菌数低減は、設備設計、原材料管理、従業員教育を統合したサニテーションプログラムで達成されます。
以下では具体的な管理ポイントを解説します。
5-1. 製造ライン設計と衛生的環境モニタリング
原料受入から包装まで一方向に流れるライン構成とし、交差汚染を防ぐゾーニングが基本です。空調にはHEPAフィルターを装備し、陽圧を維持することで外気菌の侵入を抑制します。
環境モニタリングでは月1回の落下菌試験と週1回の表面ふき取りATP測定を行い、基準逸脱時は即時清掃と再検査を実施します。
5-2. 加熱・冷却・殺菌工程の検証と乳酸利用
加熱殺菌は中心温度75℃1分を基本に、製品特性に合わせD値、z値を計算して検証します。冷却では真空冷却器や急速エアブラストで30℃→10℃を90分以内に到達させることで菌増殖を抑制できます。
近年は乳酸・酢酸を利用したpH制御で静菌化する“コンビネーションプロセス”が注目され、味への影響が少ない0.2%乳酸添加が多用されています。
5-3. 原材料管理と保存温度で菌数を抑える方法
原材料は納入時に温度とロットを記録し、先入先出(FIFO)を徹底します。冷蔵は4℃以下、冷凍は−18℃以下を維持し、庫内温度ロガーをクラウド管理してアラート設定すると逸脱リスクを低減できます。
高リスク原料(鶏肉、卵、もやし)は納品時に簡易生菌数キットでスクリーニングし、不適合品を即時返品する体制が有効です。
5-4. HACCP・食品衛生管理計画への組込みと従業員教育
一般生菌数はCCPではなくOPRP(運用前提条件)で管理するケースが多いですが、基準逸脱は重大な不適合につながるため手順書に明確な記録方法を設定します。
従業員教育では手洗い実習、サニテーションロールプレイング、VRを使った汚染シミュレーションなど多様な手法を組み合わせ、理解度テストで効果測定を行います。
5-5. 小規模事業者向け簡易測定キットの活用
簡易培地パドルやATPふき取り検査は1回数百円で実施でき、結果が15分〜48時間で判明します。法定検査の代替にはなりませんが、毎日の自主点検として活用すれば、異常検知から是正までのリードタイムを大幅に短縮可能です。
自治体によっては“簡易検査キット導入補助金”が用意されているので、コスト面で導入をためらう小規模店舗は活用を検討しましょう。
6. 基準オーバーが判明したら?検査再実施・リコールの手順
基準値を超えた場合、速やかに原因究明とロット隔離を行い、状況に応じて行政への報告義務が発生します。
以下のプロセスを標準手順書に組み込み、緊急時でも漏れなく対応できる体制を整えておくことが重要です。
6-1. 検査結果で陰性から陽性へ転じるケースと再試験
再検査で陽性へ転じる主因は検体の不均一性と保存中の菌増殖です。サンプリングはロット全体を代表する5点混合とし、冷蔵輸送で24時間以内に検査を行うことで再試験の変動を最小化できます。
結果が不一致の場合、第三者機関でのクロスチェックを実施し、最終判定を行います。
6-2. 食品回収・行政報告フロー(厚生労働省への届出)
リコール判断後は速やかに自主回収届を厚生労働省および都道府県に提出し、回収開始日、対象ロット、理由を公表します。消費者への告知はウェブサイト、店頭POP、プレスリリースを併用し、SNSで拡散することで迅速に周知を図ります。
回収進捗と再発防止策をまとめた最終報告書を30日以内に提出することが求められます。
6-3. 腸炎ビブリオ・大腸菌・サルモネラ同時検出時の具体的対応
病原菌が同時検出された場合は被害拡大防止のため即座に販売停止し、製造ラインを隔離して徹底洗浄・消毒を実施します。従業員の検便や設備の拭き取り検査を追加し、根本原因を特定後に再稼働を許可する形が望まれます。
行政指導を受けた場合は改善計画書を提出し、是正確認が完了するまで出荷を停止することが一般的です。
6-4. 企業ブランドを守る危機管理コミュニケーション
リコール時の情報開示は“早さ・正確さ・誠実さ”が鍵となります。メディアブリーフィングでは事実関係と再発防止策を具体的数字で示し、透明性を担保することでブランド信頼回復へ繋げられます。
社内外へ定期的に進捗を共有し、顧客窓口ではFAQを整備して問い合わせに即答できる体制を構築しましょう。
7. まとめと今後の法改正動向—一般生菌数基準はどう変わる?
一般生菌数基準は科学的エビデンスの蓄積と国際整合を背景に、今後も段階的に厳格化される見通しです。
事業者は法改正を待つのではなく、自社リスク評価に基づく自主基準を先行して設けることで市場競争力を高められます。
7-1. 2025年改訂ポイントと残された課題
今回の改訂では高リスクカテゴリーの基準引き下げと測定法の多様化が行われましたが、農産物や宅配食品など新たな流通形態への対応が課題として残ります。
地方自治体ごとの運用温度差を解消するため、ガイドラインの統一とデジタルデータベース化が求められています。
7-2. AI・IoTを活用したリアルタイム測定技術の展望
今後は培養を必要としない蛍光バイオセンサーや機械学習による画像判定装置が普及し、一般生菌数を30分以内で定量する技術が実用化される見込みです。IoT温度ロガーと連携した“危険温度帯アラート”が自動で送信されるシステムも登場し、食品衛生管理はリアルタイム監視時代へ移行しつつあります。
法規制側もこれら新技術を前提とした柔軟な基準設計が求められるでしょう。