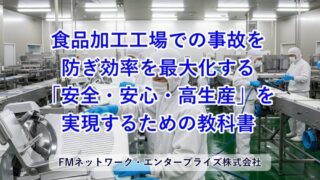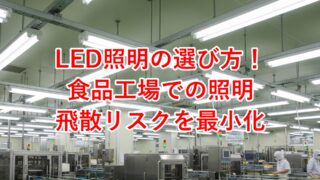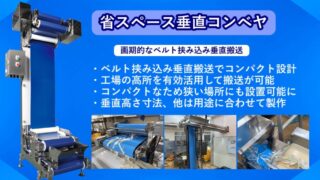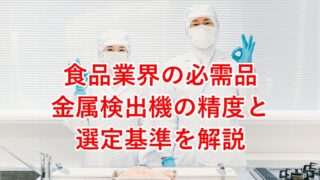食品の安全性がこれまで以上に重視される現代において、食品工場における衛生管理は事業の根幹をなす要素です。微生物制御、特に殺菌・除菌は、食中毒の予防、製品の品質保持、そして消費者の信頼確保に不可欠なプロセスとなっています。その中で、「次亜塩素酸水」という洗浄・殺菌剤が、厚生労働省によって食品添加物(殺菌料)として指定されたことは、日本の食品工場にとって大きな意味を持ちます。
しかし、次亜塩素酸水は「次亜塩素酸ナトリウム」と混同されやすく、その特性や適切な使用方法について誤解されているケースも少なくありません。厚生労働省が指定した食品添加物としての次亜塩素酸水に焦点を当て、その深掘り解説から、日本の食品工場で最大限にその効果を発揮するための具体的な活用術までを詳細に解説していきます。
1. 次亜塩素酸水とは何か?~基礎知識と食品添加物指定の背景~
まず、次亜塩素酸水とは何か、その基本的な性質と、なぜ食品添加物として指定されるに至ったのかを理解することから始めましょう。

1.1. 次亜塩素酸水の化学的・物理的特性
次亜塩素酸水(Hypochlorous Acid Water)は、電気分解や化学反応によって生成される、次亜塩素酸(HClO)を主成分とする水溶液です。その特性は、pH値によって大きく異なります。
- pH値による分類:
- 強酸性次亜塩素酸水
pH2.7未満。有効塩素濃度20~60ppm。塩酸と食塩水を電気分解して生成。高い殺菌力を持つが、金属腐食性が強く、安全性に配慮が必要。 - 弱酸性次亜塩素酸水
pH2.7~5.0。有効塩素濃度10~80ppm。塩酸と食塩水を電気分解、または炭酸ガスと次亜塩素酸ナトリウムを混合して生成。殺菌力と安全性のバランスが良く、食品添加物として広く利用される。 - 微酸性次亜塩素酸水
pH5.0~6.5。有効塩素濃度10~80ppm。塩酸と食塩水を電気分解、または炭酸ガスと次亜塩素酸ナトリウムを混合して生成。食品添加物の主流であり、高い安全性と効果を両立。
- 強酸性次亜塩素酸水
- 殺菌メカニズム
次亜塩素酸(HClO)は、細胞膜を容易に透過し、微生物の細胞内に入り込みます。細胞内で、タンパク質や核酸、酵素などを酸化・変性させることで、微生物の機能を破壊し、殺菌効果を発揮します。次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の主成分である次亜塩素酸イオン(ClO⁻)よりも、次亜塩素酸(HClO)の方が約80倍もの殺菌力を持つとされています。pHが低いほど次亜塩素酸の存在比が高まるため、弱酸性~微酸性の領域で高い殺菌力を発揮するのです。 - 安全性
有機物と反応すると速やかに水に戻る性質があり、残留性が低いことが特徴です。また、誤って飲用した場合でも、胃酸と反応して不活性化されるため、人体への影響が少ないとされています。この高い安全性が、食品添加物として指定された大きな理由の一つです。
1.2. 食品添加物としての指定と法的根拠
厚生労働省は、次亜塩素酸水を「食品添加物(殺菌料)」として2002年6月10日に指定しました。これは、食塩水を電気分解して得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液として認められたものです。
- 指定の目的
食材や調理器具などの殺菌に用いることで、食中毒菌の増殖を抑制し、食品の安全性を向上させることを目的としています。 - 使用基準
食品添加物として指定された次亜塩素酸水には、厚生労働省令によって使用基準が定められています。- 対象: 野菜、果物、魚介類など、様々な食品の殺菌に用いることができます。
- 有効塩素濃度: 使用する次亜塩素酸水の有効塩素濃度には上限が設けられています(例:通常80ppm以下、一部では200ppm以下)。
- 使用方法: 殺菌後は、必ず水で洗い流すか、拭き取るなどの措置が必要とされています。次亜塩素酸水自体が食品に残存しないようにすることが重要です。
- 表示義務: 食品添加物として使用した場合、最終製品にその旨を表示する義務が生じます。
1.3. 次亜塩素酸ナトリウムとの違い
しばしば混同される次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる「漂白剤」や「ハイター」の主成分)とは、全く異なるものです。
- pH値
次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性(pH11~13)ですが、次亜塩素酸水は酸性(pH2.7~6.5)です。 - 主成分
次亜塩素酸ナトリウムは次亜塩素酸イオン(ClO⁻)が主成分ですが、次亜塩素酸水は次亜塩素酸(HClO)が主成分です。この違いが、殺菌力と安全性の決定的な差となります。 - 殺菌力
同一有効塩素濃度であれば、次亜塩素酸水の方が次亜塩素酸ナトリウムよりもはるかに高い殺菌力を持ちます。 - 安全性・残留性
次亜塩素酸ナトリウムは高いpHと塩素臭が強く、残留性も高いため、食品に直接使用するには制限があります。一方、次亜塩素酸水は安全性と残留性の低さが特徴です。 - 金属腐食性
強酸性次亜塩素酸水を除き、次亜塩素酸水は次亜塩素酸ナトリウムよりも金属腐食性が低い傾向にあります。
この違いを正しく理解することは、食品工場で次亜塩素酸水を適切に導入・活用する上で非常に重要です。
2. 次亜塩素酸水の効果と優位性~食品工場におけるメリット~
食品工場で次亜塩素酸水を導入することには、多くのメリットがあります。

2.1. 幅広い微生物への効果
細菌、ウイルス、真菌(カビ)、酵母など、様々な微生物に対して高い殺菌効果を発揮します。
- 食中毒菌への効果
大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、セレウス菌、カンピロバクターなど、主要な食中毒菌に対して有効です。ノロウイルスなどのエンベロープを持たないウイルスにも効果が期待できます。 - 芽胞形成菌への一定の効果
枯草菌やウェルシュ菌などの芽胞形成菌に対しても、次亜塩素酸ナトリウムよりは効果が期待できますが、完全な不活化には限界があるため、加熱殺菌などとの併用が推奨されます。
2.2. 高い安全性と環境負荷の低減
食品添加物として指定されていることからもわかるように、その安全性は大きな利点です。
- 人体への安全性
有機物と反応して水に戻るため、皮膚刺激が少なく、万が一、目に入ったり、経口摂取したりしても、次亜塩素酸ナトリウムに比べて安全性が高いとされています。 - 環境への配慮
使用後は速やかに分解されるため、排水による環境負荷が低いと言えます。
2.3. 低い金属腐食性と素材への影響
微酸性~弱酸性領域の次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウムに比べて金属腐食性が低く、設備の劣化リスクを軽減できます。
- 設備への優しさ
ステンレス製の調理器具や生産ライン、床材などへの影響が少ないため、幅広い場所での使用が可能です。ただし、強酸性次亜塩素酸水や、長時間・高濃度での使用は腐食の可能性があるので注意が必要です。 - プラスチック・ゴム製品への影響
ほとんどのプラスチックやゴム製品に対しても、変質や劣化のリスクが低いとされています。
2.4. 脱臭効果
アンモニア臭や生ゴミ臭など、食品工場で発生しやすい不快な臭気の原因となる物質を酸化分解することで、高い消臭効果を発揮します。これは、作業環境の改善にも繋がります。
3. 日本の食品工場における次亜塩素酸水の活用術
次亜塩素酸水の特性を理解した上で、日本の食品工場においてどのように効果的に活用できるかを具体的に解説します。

3.1. 原材料・資材の殺菌
- 野菜・果物の殺菌
カット野菜工場などにおいて、一次洗浄後に次亜塩素酸水(有効塩素濃度10~50ppm程度)に浸漬殺菌します。浸漬後は、必ず清浄な水で十分にリンス(すすぎ)を行い、残留塩素を除去します。これにより、表面に付着した食中毒菌や腐敗菌の数を大幅に減らし、製品の鮮度保持と安全性を高めます。 - 魚介類の殺菌
鮮魚加工場などで、魚介類(特に生食用のもの)の洗浄・殺菌に用います。タウリンやアミノ酸などの有機物が多い魚介類に対しては、次亜塩素酸水の有効塩素濃度が速やかに低下するため、定期的な交換や濃度の確認が重要です。 - 鶏卵の殺菌
卵表面のサルモネラ菌対策として、洗卵工程での次亜塩素酸水の使用が効果的です。 - 包装資材・容器の殺菌
空のプラスチック容器、瓶、運搬用コンテナなどの洗浄・殺菌に使用します。特に、リターナブル容器を使用する場合に有効です。
3.2. 製造ライン・設備の殺菌
- カッター、スライサー、ミキサーなどの殺菌
使用後の洗浄に加え、次亜塩素酸水(有効塩素濃度50~80ppm程度)での浸漬やスプレー噴霧により、刃物や部品の殺菌を行います。分解可能な部品は、分解して浸漬殺菌することで、より効果が高まります。 - コンベアベルトの殺菌
定期的な洗浄後、次亜塩素酸水を含ませた布で拭き取るか、スプレーで噴霧して殺菌します。 - 配管・タンク内部のCIP(定置洗浄)
循環洗浄システムに組み込むことで、配管やタンク内部の微生物バイオフィルムの形成を抑制し、徹底した衛生管理を実現します。ただし、配管材質によっては適さない場合もあるため、事前確認が必要です。 - 冷却水・加湿水への添加
冷却工程や加湿工程で使用する水に、低濃度の次亜塩素酸水を添加することで、水系微生物の増殖を抑制し、製品への汚染リスクを低減します。
3.3. 作業環境の殺菌・消臭
- 床・壁・ドアノブなどの殺菌
日常的な清掃に加え、次亜塩素酸水(有効塩素濃度80~200ppm程度)を噴霧または含ませた布で拭き取ることで、環境中の微生物数を減らします。特に、生鮮食品を扱うエリアや、交差汚染のリスクが高いエリアで有効です。 - 長靴、手袋などの殺菌
作業員の長靴や洗浄可能な手袋などを、次亜塩素酸水に浸漬殺菌します。 - 空中噴霧による空間除菌・消臭
食品加工室の空気をクリーンに保つため、専用の噴霧器を用いて低濃度の次亜塩素酸水(有効塩素濃度10~20ppm程度)を空間に噴霧します。これにより、浮遊菌の抑制や、不快な臭気の除去が期待できます。ただし、過剰な噴霧は作業者の体調に影響を与える可能性もあるため、換気を十分に行い、適切な濃度と噴霧量を守ることが重要です。
3.4. 作業員の衛生管理
- 手洗い後の手指消毒
石鹸による手洗い後、次亜塩素酸水(有効塩素濃度50ppm程度)で手指を洗浄・消毒します。アルコール消毒が苦手な作業者にも利用しやすいというメリットがあります。 - うがい
低濃度(10ppm以下)の次亜塩素酸水でのうがいを推奨し、口腔内の衛生管理を促進します。
4. 次亜塩素酸水導入・運用上の注意点と管理体制
次亜塩素酸水を最大限に活用するためには、その特性を理解し、適切な管理体制を構築することが不可欠です。

4.1. 有効塩素濃度の管理
次亜塩素酸水は、時間経過や有機物との反応、紫外線 exposure によって有効塩素濃度が低下しやすい性質があります。
- 有効塩素濃度測定
専用の測定器や試験紙を用いて、使用前の有効塩素濃度を必ず測定し、基準値内であることを確認します。 - 生成機の選定
高品質で安定した濃度の次亜塩素酸水を生成できる装置を選定することが重要です。必要に応じてオンサイトでの生成機導入も検討します。 - 使用期限の管理
生成された次亜塩素酸水には有効期限があります。古くなったものは廃棄し、常に新鮮なものを使用するようにします。
4.2. pH値の確認
次亜塩素酸水の殺菌力はpHに大きく依存するため、定期的にpH値を確認することも重要です。
4.3. 保管方法
直射日光を避け、冷暗所で密閉して保管します。紫外線は有効塩素を分解し、殺菌力を低下させます。
4.4. 従業員への教育
次亜塩素酸水の正しい知識、使用方法、保管方法、安全上の注意点について、全従業員に対する徹底した教育が必要です。次亜塩素酸ナトリウムとの違いを明確に伝え、誤使用を防ぐ啓発活動も行います。
4.5. 定期的な効果検証
次亜塩素酸水の使用前後で、微生物検査(拭き取り検査、落下菌検査など)を実施し、殺菌効果が適切に得られているかを定期的に検証します。これにより、使用方法や濃度設定の最適化を図ることができます。
4.6. 法規制の遵守
食品添加物としての使用基準、作業環境における労働安全衛生法、排水に関する環境法規など、関連する法規制を常に遵守し、適切な運用を行います。
5. 優れた「殺菌力」と「安全・安心」を実現した次亜塩素酸水生成装置ガーディアンロック
次亜塩素酸水の効果を最大限に引き出すには、最適な濃度管理の元での生成が不可欠となりますが、「次亜塩素酸水生成装置ガーディアンロック」は、まさにその課題に応えるための装置で、食品工場の衛生管理を革新し、安心・安全な食品製造を実現するための手助けとなります。
次亜塩素酸水生成装置ガーディアンロックと次亜塩素酸ソーダの違いは、実はpHだけです。しかし、ガーディアンロックには殺菌に必要な有効遊離塩素が多く存在するために、殺菌力はなんと次亜塩素酸ソーダの主成分と比較して70倍(理論値)にもなり、一般的に強いと言われている芽胞細菌にも低濃度で効果を発揮します。
それぞれの食品工場にあわせたご提案が可能ですので、次亜塩素酸水生成装置ガーディアンロックの詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。
6. まとめ:次亜塩素酸水で拓く食品工場の新たな衛生管理
厚生労働省が食品添加物として指定した次亜塩素酸水は、その高い殺菌力と安全性、そして環境負荷の低さから、日本の食品工場にとって非常に有効な衛生管理ツールとなり得ます。原材料から製造ライン、作業環境、そして作業員の衛生管理に至るまで、幅広い用途での活用が期待されます。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、次亜塩素酸水の化学的特性を正しく理解し、有効塩素濃度やpHの管理、適切な使用方法、そして従業員への教育といった、厳密な運用管理が不可欠です。
食品の安全に対する消費者の意識が高まる中、次亜塩素酸水は、食中毒のリスクを低減し、製品の品質と鮮度を保ち、結果として企業のブランドイメージと信頼性を高めるための強力な武器となるでしょう。
貴社の食品工場においても、次亜塩素酸水の導入を検討し、その特性を最大限に活かした衛生管理体制を構築することで、安心・安全な食品提供に貢献できることを願っています。